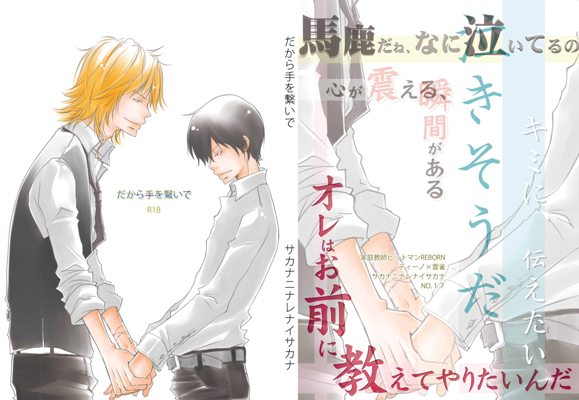
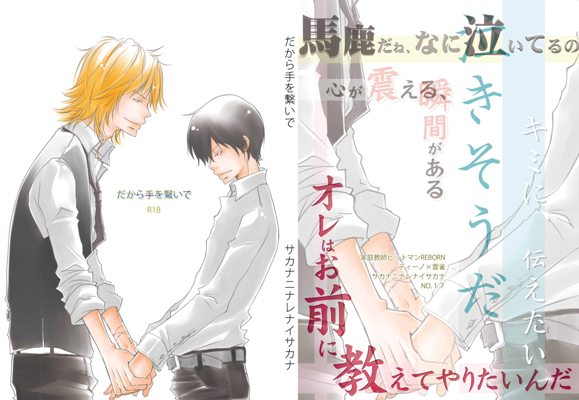
【だから手を繋いで】 より sample
| ディーノと手を繋ぐ時、それは、実に様々な思いを雲雀にもたらす。 たとえば、温もり。 寒さに凍えそうな冬の盛り、無駄に体温が高く、冬場でも平然と薄手のシャツ一枚でふらふらしているような男の体温は、末端冷え性で指先の痺れに苛立つ雲雀の指先を、ぬくぬくと温める。 オレは恭弥専属のホッカイロだな。 そう言って笑う男のしたり顔に腹が立って、適度に殴りつけておきながらも、冬場の盛り、このホッカイロは実に役に立った。 冬が、鬱陶しいだけの季節ではなくなっていたのはこの頃からだ。 たとえば、意外に筋張った大きさ。 いたずらっ子の様な笑みで、ぐいっと引き寄せられて強引に手を繋がれてしまうと、雲雀の力では、なかなか振り解くことが出来なくなる。 強引に封じ込まれてしまうのは、いいようにされているようで我慢ならなかったが、繋いだ手から伝わる体温はいつでも暖かく雲雀を満たすので、これはこれでいいのかもしれないと思う。 男の大きな手は、ただ強引なだけではなく、いつでも本人同様、異様なまでの気遣いを感じさせた。 たとえば、ただ繋いでいるだけで流れていく時間の心地よさ。 何をするでもない。 お互い、過剰に言葉を並べたてるでもなく、そこに理由を作るでもなく、ただ、そこにあるだけの時間。 意外な心地よさは、温もり同様、じんわりと雲雀を満たしていく。 それはまるでぬるま湯のような、記憶にない母の胎内の様な、淡く小さな心地よい瞬間。 ぐぬりと.入ってくる男の凶暴な隆起は、雲雀からすべての思考と抵抗を奪うものだった。 「恭弥……頼む、から……力、抜いて……っ」 出来るわけがないと思った。 全身が強張って、それどころではなかった。 情けなくもただ喘ぐしかない雲雀の後方に、上からのしかかり、我が物顔で突き入れておきながらも、男はあくまでも、伺うような響きを止めないでいる。 「……っい…っつ……っ!」 雲雀の口から洩れるのは、もはやみっともない喘ぎと呻きでしかない。 散々、これでもかという程にほぐされ、舐められ、かき混ぜられて、ドロドロになったところをようやっと迎え入れたのだ。 もう少しすんなりと入るかと思ったが、雲雀の身体が思う以上に強張っているのか、そこは驚くほどに、ディーノの侵入を拒んでいた。 どれだけ時間をかけたか分からない。 これ以上はないという程、ほぐされた筈だった。 なのにこの期に及んで、そこは受け入れることを拒むのかと、雲雀は半ば泣きそうな思いでぎゅっと目を閉じるのだ。 すると、ふわりと浮きあがるような感覚と、指先から首の裏までを一気に駆け抜ける痺れが雲雀を襲い、ああ、またあれが来るのか、と思う。 耳鳴りと痺れ。点滅する光と遠のく意識。 息が出来なくなり、喉が鳴り、ただ喘ぐしかない、あの恐怖。 小さく喉を鳴らしたところで、すかさずぎゅっと手を繋がれた。 驚いてゆっくりと目を開けると、飛び込んできたのは、無駄に光を背負った男の、眩いまでの黄色だった。 「大丈夫だ、大丈夫だ、恭弥。……オレは……ここに、いる」 本当だと思った。 男はここにいる。 繋がれた手から伝わってくるのは、紛れもない、ディーノの温もりだった。 指と指を絡め、殆どしがみつく様に力を込める。 来ると思った発作はいつの間にか消えていて、代わりに熱い、発火しそうに熱い熱が、雲雀の体内を駆け抜けていく。 荒い息は、もはや息苦しさによるものではなかった。 「大丈夫だ……大丈夫だから……力を抜いて、恭弥…っ」 男の熱い囁きに、雲雀はなんとか意識して力を抜こうと試みる。 大きく何度も息を吐き出す。 何度目かの深呼吸の際、まるで呼吸を合わせるかのように、ディーノが奥深くまで、一気に侵入してきた。 「……っ!」 「……ん……もう、ちょ、い……っ」 「や……っあ……む、り……っ」 喘ぐ雲雀だったが、言葉とは裏腹に、それはじんわりと、雲雀の中、馴染んでいくようだった。 「恭、弥……わかる、か? 今、お前の中……入ってる……っ」 「ん……ふぅ……っん……」 「す、げ……中、すっげー動いてる……あんま、動かすなって……っ」 出ちまう。耳元で囁かれて、雲雀はかっとなる。 「……んの……っ」 恥ずかしい事を、耳元で囁くなと思う。 そうでなくとも、羞恥で死にそうになっているのだ。 身体を重ねたことなどこれまで何度だってあったし、いい加減慣れてもよさそうなものなのに、いつだって雲雀は、死にたくなるような恥ずかしさと、言いようのない熱さを、男に対して感じるのだ。 しっとりと汗ばんだ肌と肌、直接触れる男の肌は、発火しそうな程に熱く、まるで火傷しそうだった。 「なあ……動いても……いい?」 「だ、から……聞く、なって、言ってる……っ!」 耳たぶを嬲るように弄びながら囁いてくる男に、かっとなって噛みつくように言葉を返す。 まるで言葉攻めのように、恥ずかしい言葉の数々で雲雀を煽る男の存在が、たまらなく憎いと思った。 男はくすりと笑った後、雲雀のあられもなく拡げた両足の太ももに手を添えると、ゆっくりと動き始める。 最初は、傷つけないよう、痛みを感じないようゆっくりと。その内、雲雀の中が異物の存在に慣れ、むしろ引き込むように伸縮を繰り返し始める頃には、だんだんと動きを早め、しまいには、ぐじゅぐじゅと水音が響き渡る程に激しく、突き入れるように、押し広げるように何度も。硬くて凶暴な肉棒をこすり上げるように、何度も出し入れする。 「……んあっ……ん…っふ…ぁ……っ!」 「ん……す、げ……気持ち、いい……っ」 「……はぁ……っや、…も……や、だ……っ!」 「もう、ちょっと……っん……や、べ……っ」 こすられるそこが酷く痺れて、ぐじゅぐじゅと卑猥な水音が益々大きく響き渡って、雲雀はもはや、何も考えられなくなる。 最初は気遣うようだった男の動きも、いまでは、自身の快楽を追うのみになっているようだった。 それは雲雀もそうだった。 男のもたらす動きが、熱が、男の夢中になって腰を振る様が、雲雀にどうしようもないくらいの満たされる感じを与える。 「……恭、弥……っん…っ……いい? ……んっ」 「…は……っあ……ん……そ、こ……ん、…いい…っ!」 「…ご、め……もう、イく……っ」 ディーノの動きが益々早くなって、もはや、打ちつけられているとしか言いようのない激しい動きだった。 お互い、鼻から抜けるような、必死の声しか出ない。 先に果てたのは、雲雀だった。 突き入れられる最中、ふと気まぐれのように触れてきた男の手で、自身を握られた瞬間、あえなく、悲鳴のような喘ぎと共に、びくびくと全身を戦慄かせて、数回に分けて白濁を放出した。 足の指先から腰の辺りまで、痺れるような快楽の波が一気に駆け上がり、きゅっと力を入れてイったからだろうか、その絞るよう な動きに、ディーノもまた、呻くような声をあげて、遅れること少し、雲雀の中に濃厚な液を吐き出した。 震えるようにして、最後の液が絞り出されるまで、全身を震わせて出し切る。 ディーノの手によって絞り出された雲雀の白濁は、雲雀の腹を、まき散らすようにして汚した。 「…んっ……や、あ……っ」 出してしまえば、すぐに襲ってくるのは羞恥の波だ。 こんな風に、あられもなく足を拡げた状態でいいように突き入れられ、白濁をまき散らし、雲雀はいっそ消えてしまいたいくらい恥ずかしい。 けれど、雲雀が何かを思うまでもなく、ずしりとのしかかるようにしてきた男の重みが、熱が、それをどこか軽くしてくれる。 男の重みは、心が満たされる感じに似ていた。 |
| サカナニナレナイサカナ ■ 畝ちうさ |